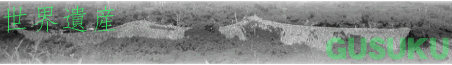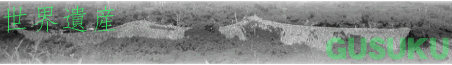|
今帰仁城跡歴史散歩
今帰仁城跡には、いくつかの歴史を語るポイントがあります。
ここではそのポイントを紹介しています。今帰仁城跡を訪れるときは、このページを読んでから行くと、今帰仁城跡の歴史を感じることができるはず。
歴史散歩は7ページあります <1> <2> <3> <4> <5>
<6> <7>
石 垣
 今帰仁城跡の石垣の特色はその特殊な積み方、つまり野面
積にある。石材の特質や、あまり手を加えていない自然石をそのまま使った荒っぽさのなかに、屏風型に美しい曲線を描いて造りあげたところにある。 今帰仁城跡の石垣の特色はその特殊な積み方、つまり野面
積にある。石材の特質や、あまり手を加えていない自然石をそのまま使った荒っぽさのなかに、屏風型に美しい曲線を描いて造りあげたところにある。
この荒い自然石を工学的にうまく利用した先人の後術が偲ばれ、文化財として十分
な価値があり、われわれはそれを継承し、長く保存しておきたいものである。
大隅あたりは比較的平坦であるが、志慶真門のあたりになるとよくもあの絶壁上にあのような石垣を積みあげたものだと、当時の技術の勝れていることとあわせて、北山王がそれだけの人員を駆使し得た権力の大きさと、人民の労苦が偲ばれる。言い伝えによると、13世紀頃に築かれたといわれるが、その怕尼芝から攀安知に至る三代94年の間に大修築がなされたというから短年月で出来上ったのではなく、「北山世の主」各代毎にしだいに増築していって現在のような大規模なものになったのではなかろうか。
その長さは約1.5kmあって首里城に次ぐ規模の大きさを誇っている。 また駐車場の北側と、115号線の県道をへだてた南西側に外壁らしい石垣が現存している。
一時期ここから石が土木工事等で取りはらわれたり、使用されたりして散逸し、崩壊したのはかえすがえすも惜しまれる。
平郎門から左へ大隅をとおて展望台下までの石垣は1960年頃、当時の琉球政府によって修築されているが、この史跡を保存するために、将来は崩壊箇所を補強していくことが計画立案されている。
平郎門
平郎門は今帰仁城跡の正門で、その名称は『琉球国由来記巻15』に、「北山王者、本門、平郎門ヲ守護ス」とでている。
この門は、1962年頃に修復されているが、修復にあたっては現在の参拝道にあわせるために南に約30cm寄せられている。
また、門の根石は現在よりも約1.5mも下に埋まっている。(修復当時の工事者の談)。修復前は上部の石垣はなく門の両端の高い石垣のみであった。
カ−ザブ
 カ−サブは、平郎門からはずれた右側のくぼ地になったところをいう。ここは、
一段と低い所でその両側は切岸状に切り立って一種の「谷底」の感じがする。石壁のとこ
ろどころには、人骨が納められている。 この地名の語源は「川さこ」つまり、川の谷間であるという(村史)。現状では木と竹でおおわれている。かつて、溜井戸の役目をなしていたかどうかについては不明であるが、興味のあるところである。 カ−サブは、平郎門からはずれた右側のくぼ地になったところをいう。ここは、
一段と低い所でその両側は切岸状に切り立って一種の「谷底」の感じがする。石壁のとこ
ろどころには、人骨が納められている。 この地名の語源は「川さこ」つまり、川の谷間であるという(村史)。現状では木と竹でおおわれている。かつて、溜井戸の役目をなしていたかどうかについては不明であるが、興味のあるところである。
<1> <2> <3> <4> <5>
<6> <7>
|